今日はいよいよ妻のおじいさんが住んでいた河南省の新郷に向かいます。
とは言え、おじいさんが新郷のどこで何をしていたのか皆目見当もつきません。そこであまり難しいことは考えず、どこか観光名所に行って「新郷に行った」とすることにしました。事前に調べると、新郷には「宝泉」という景勝地があるようよし。太行山脈の南端部分にあたり、さながら中国版グランドキャニオンのような景色が広がっているんだそう。それはいいじゃないのーということで「河南宝泉旅遊区」に行くことにしました。
鄭州から宝泉まではバスを利用します。鄭州のバスターミナルを午前8時に出発するチケットを予約。余裕を持ってホテルを出たつもりですが、意外と時間ギリギリになりました。
いざ改札口でスマートフォンの予約画面を提示したところ、女性スタッフから紙のチケットに交換してくるよう言われ、チケット売り場に並び直し。で、いざ紙のチケットを提示したら、今度は身分証を提示しなさいとのこと。そこでパスポートを見せると「身分証ですよ、身分証」と言います。中国では国民1人に1枚、身分証が発行されています。日本のマイナンバーカードみたいなもので、さまざまな手続きの際に使え、高速鉄道の改札口も身分証をタッチすれば通過できます。でも身分証を持っているのは中国人の話。外国人には発行されないので、私たちの身分証はあくまでパスポートです。
だのに「身分証はないのか」とか何とか言ってくるので、私も少しイライラしてきちゃって「外国人が中国の身分証を持っているわけがないだろう」「バスの発車まで時間が無い」と少し声を荒げてしまいました。すると何とか私は通過できましたが、そのスタッフ、今度は妻のパスポートを持ってどこかへ行こうとします。で、また思わず「どこに持って行くのか」と叫んでしまいました。するとスタッフは「本当にこれで通していいのか、警察に確認する」と言います。結局「問題ない」ということですぐに戻ってきましたが……いやはや、当たり前でしょ。
それにしてもスタッフが偉そうだったこと。まるで「改札を通すも通さないも私の一存」と言わんばかりの態度でした。この国には「自分に与えられた権利」を行使するのが好きだという人が一定数います。なぜなんでしょう。「権力=我が意のまま=偉い」みたいな発想になってしまうのかな。

鄭州から1時間少しで宝泉に着きました。宝泉は観光地として整備されていて、谷底の川のほとりを散策できる「大峡谷」エリアと、崖上部から景色を一望できる「崖天下」エリアの2つに分かれています。私たちは「大峡谷」エリアから入ることにしました。
ここ宝泉は立派な峡谷で、切り立った崖が印象的です。ここを流れている川は「峪河」と言うそうです。ところどころ堰堤があったので、厳密にはダム湖みたいな感じかもしれません。

とても暑かったですが、水辺にいると涼しく感じます。川を横切る橋を渡ると中央付近で風が吹いて気持ちいいです。崖と崖の間で風の通り道になっているんでしょうか。

夏休みだけあって人はそこそこいました。けれど全国に名の知れた観光地に比べればマシです。例えば四川省の九寨溝はこんなもんじゃないでしょうね。芋洗い状態だったと思います。その点、ここ宝泉は穴場スポット。中国で観光地の人出がこの程度なら御の字だと思います。

崖沿いに“L型洞穴电梯”(L字型洞穴エレベーター)なるものがありました。これに乗ると谷底から崖の上まで一気に移動できます。
L字型という名前の通り、洞窟に入るとまず400メートルほど水平な道があって、突き当たりにエレベーターがありました。エレベーター自体は普通のエレベーターで、あっという間に崖の上に着きました。乗っていると気付かなかったのですが、実は336メートルの距離を上っていたようです。中国で運行距離が最も長い観光エレベーターなんだとか。

崖の上まで来るとこんな感じ。まさに絶景――中国版グランドキャニオンです。
標高は平均で1150メートルあるとのこと。高いことは分かるのですが、建物といった人工物が見えないので感覚が麻痺しちゃって、あまり高くないように感じてしまいます。

やって来たのは今日宿泊する「黄岩根民宿」です。景勝地の中には何軒か宿泊施設があり、こちらはそのうちのひとつです。北京にいる段階からWeChatでやり取りをし、宿付近は商店がないから必要なものは買ってきたほうがいいとか、宝泉から帰りのアクセスはどんな交通手段があるとか、いろんなことを教えてくれたので大変助かりました。

中国で民宿と名のつく宿に泊まるのは少し勇気がいりそうですが、こちらは清潔で快適でした。畳の小上がりもあって、くつろげるスペースも十分。
部屋で過ごしていると民宿のスタッフさんが果物の盛り合わせを持ってきてくれました。それだけでなく室内の冷蔵庫に入っている飲み物が全部無料だったり、無料の顔パックなどアメニティーが充実していたり、さりげないサービスがうれしいですね。

部屋にはベランダもあって、景色はこんな感じ。いやあ、絶景です。1台のテーブルと2脚のイスが置いてあり、景色を眺めながらくつろげるようになっていました。実はこちらの景色が見える部屋は少し「お高い」のです。しかしこれなら支払った甲斐があるというものです。
ベランダからは帰路に就く観光客の姿がたくさん見えました。そして人はどんどん少なくなり、最終的に誰一人いなくなりました。静かな景勝地をベランダからまったり眺めていると、まるでこの絶景を独り占めしているような贅沢な気分になります。

夕食は民宿の食堂でいただきました。これがどれも素朴なんだけど、どれも今までに食べたことのない独特の味わいでとてもおいしかったです。
右奥の料理はおそらくシソの葉を揚げた料理。天ぷらみたいなサクサクした食感で、おつまみにピッタリです。左手前の料理は“猎肉炒山笋”と書いてあったので、おそらくイノシシやシカのような獣肉を使っているんだと思います。全然臭みはなく、タケノコと一緒に炒めてあって山の滋味を味わいました。あと左奥の料理は“槐花炒土鸡蛋”。“槐花”というのはエンジュの花で、中国北方では初夏に食べる伝統食材なんだそうです。卵と一緒に炒めていて、とても香り豊かでした。
夜は娘を寝かせつけた後、ベランダでビールをいただきました。残念ながら真っ暗で峡谷は全く見えませんでしたが、星空はきれいでした。地元の岡山に住んでいた頃はもっと星空に親しんでいたように思いますが、その後、岡山を離れてからというもの、こうして星をまじまじと見たのは久しぶりな感じ。東京や北京じゃ明るい星しか見えませんもんね。
ベランダで妻とゆっくりしていると、午後11時を過ぎた頃に別の宿泊客たちが民宿の中庭にやって来ました。で、着衣のままプールに入ってキャッキャッ大騒ぎ。ちょっとびっくりするくらいうるさかったです。家族連れなのかな?家族連れと言っても、子どもは小学生や中学生じゃないですよ。成人しているかな?というくらいで、親に至っては50、60代と思わしき年代。皆さん、大声をあげながらプールでバシャバシャはしゃいでいるのです。
ちょっとぉ……せっかく良い雰囲気だったのが台無しです。そもそもこんな時間に騒いだら他の宿泊客に迷惑でしょう。ベランダにいる私たちにも気付いているようでしたが、全然お構いなしでした。民宿のスタッフも聞こえたんじゃないかしら。この騒がしさは民宿側が注意すべきです。これについては私、クレーム入れさせていただきます。
追記)
民宿側に「うるさい宿泊がいて、民宿が注意すべきだった」とクレームを入れました。すると先方からは“深夜噪音问题,会加强夜间巡查,遇到类似情况第一时间温和提醒,守护安静氛围”(深夜の騒音問題については夜間の巡回をさらに強化し、同様の事態があればすぐに穏やかにお声がけいたします。お客様の静かなご滞在環境を守るために努めてまいります)という回答がありました。ほんまかいな(^^;)。けど雰囲気はいい民宿だったので、ぜひ今後の改善に期待したいと思います。













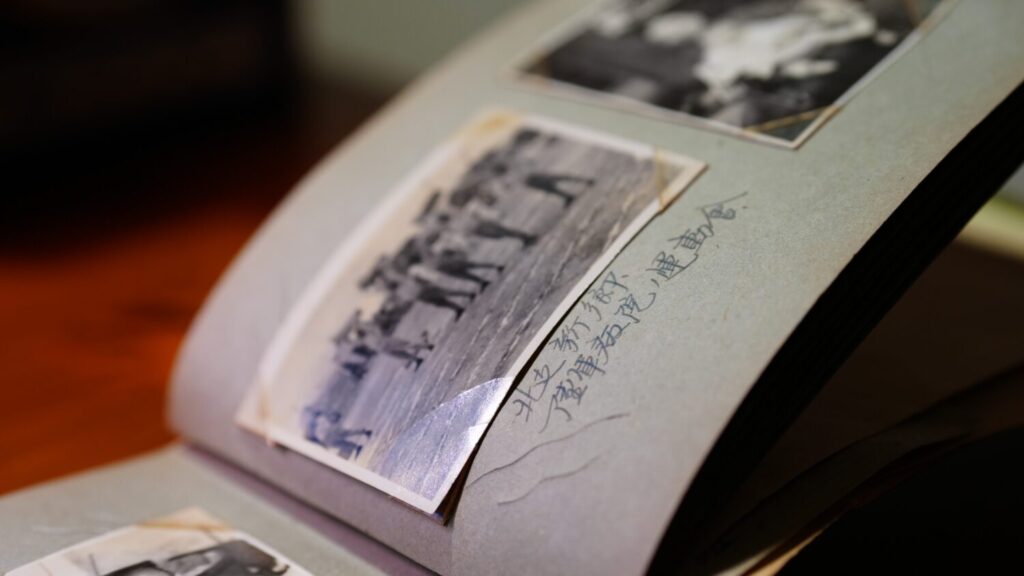



最近のコメント