日本から中国に来た人がよく「中国には回転ドアがたくさんありますね」と言います。回転ドアというのは商業施設の入口なんかにある、人が出入りする際に自動でクルクル回転する扉のことです。
中国に回転ドアがたくさんあると言うより「日本で回転ドアを見かけなくなった」と言うのがより正確かと思います。
その理由は私と同世代、あるいはそれ以上の世代の方であればご存じの方も多いと思います。2004年、東京の六本木ヒルズで幼い子どもが回転ドアに挟まれて亡くなるという事故が起きました。閉まりかけたドアに駆け込んだ際に上半身が挟まれ、ただちに救出されたものの、まもなく亡くなりました。よく知る場所で起きた事故だったこともあり、私もよくニュースを覚えています。この事故をきっかけに、全国各地の回転ドアは急速に姿を消していきました。
これを思い出す度に、とても「日本らしい」と感じます。日本では特定の製品に関してひとたび事故が起きれば、原因が究明されるまで運用や供給がストップされます。中国は正反対。事故が起きても運用や供給が止まることはないどころか、時には事故そのものが隠蔽されてしまいます。
中国では最近、スマートフォンメーカー「シャオミ」の自動車が起こした事故が大変注目されています。そもそも多くの日本人は「スマホメーカーが自動車を作っているの?」という点に驚いちゃうと思いますが、中国ではシャオミだけでなくファーウェイも車を作っていますし、ドローンメーカーのDJIも作っていて、街中ではよく見かけます。
今回の事故はシャオミのSU7という電気自動車が起こしました。3人の女子大学生が運転支援機能を使って時速116キロで走行していたところ、システムが前方で工事箇所を検知しました。車は自動で減速を始め、その1秒後に運転手が自ら制御する形でブレーキを踏み始めたものの、間に合わずに衝突したということです。
昨今、自動車の自動運転・運転支援がもてはやされていますが、私はまだまだ不十分な技術だと思っています。そもそも新興のスマホメーカーが作った自動車です。それなりの検証を経て販売されているのだと思いますが、安全技術の蓄積は日本やドイツといった自動車大国のそれにはかなわないでしょう。現にヨーロッパは自動運転に関する法律が大変厳格です。データや仕様のコンプライアンス、実証テストのルール、事故が起きた際の責任の所在、どれも厳しく定められています。テスラの完全自動運転機能がヨーロッパで広く普及していないのがその一例です。
もちろん中国の規制少ない環境が技術開発に一役買っているのは重々理解しています。実際、中国の自動運転・運転支援の実用化は世界トップクラスです。その一方、事故が起きた後も毎日のようにシャオミのSU7を見かけます。亡くなった3人の遺族はどう思うでしょう。街中で同型車種を見かける度、日本の回転ドアをめぐる対応との違いを思い出さざるを得ないのです。



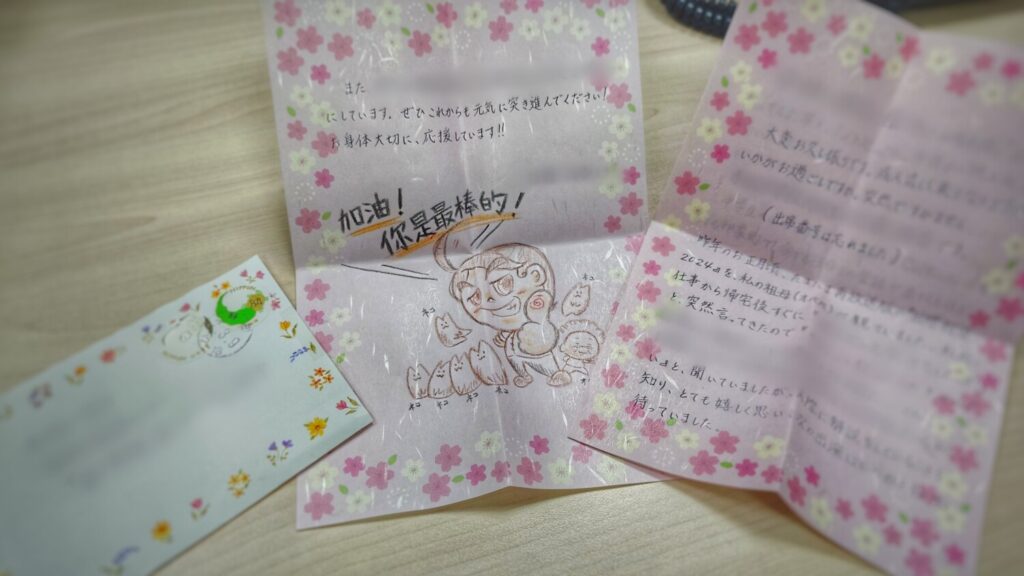
最近のコメント