ここ最近、北京では暑い日が続いています。気温が35度近くなる日もあるほど。けれど日本と違って「立っているだけで汗が噴き出る」ということはありません。おそらく日本より乾燥しているからでしょうか。とは言え、ジリジリと容赦なく照りつける強い日差しは体力を容赦なく奪います。
こういう日は外出するのが億劫になります。昼食も外食せず、デリバリーで届けてもらって涼しい室内で……なんて思っちゃいますが、私はやはり外に出ます。昼食のときくらい外に出ないと全然歩かなくなっちゃうんですよね。
どこでお昼を食べようかなと歩いていたとき、こんな光景を目にしました。ある建物の門の前に机が置かれ、そこに食事のデリバリーが並んでいます。建物によっては出前の配達員が中に入るのを禁止しているところがあり、その代わりに入口付近に机や棚を設置して「ここに置いてください」という仕組みになっているのです。注文した人は、その場所まで自分で取りに行くことになります。
ただ私はこれを見て、炎天下の中、こうして食事が放置されることで傷んでしまわないか気になってしまいました。そもそも自分が食べるものが誰でも触れられるような場所に置かれていることにも些か抵抗があります。中国はレストランで食べきれなかった料理を持ち帰る“打包”文化がありますが、日本でこれが根付かなかった背景には衛生面への懸念があったとも言われています。最近は中国でも健康や衛生への意識が高まっていますから、こうした風景もいずれ見られなくなるんじゃないかなあと個人的には思っています。

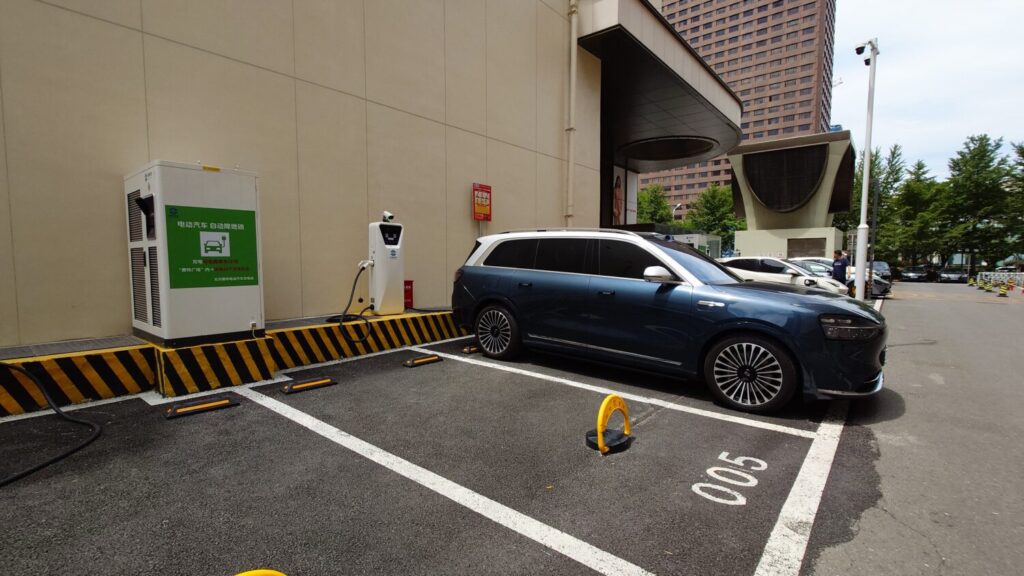




最近のコメント