タイトルの中国語は「小児科病院で見かけるあれこれの人間模様」みたいな意味です。
私の職場の近所には中国有数の小児科病院があり、中国各地から診察に訪れた親子連れの姿を多く見かけます。都会風のファッショナブルな服装に身を包んだ親子、おそらく農村から出て来たのであろう素朴な格好の親子、本当にあれこれの人間模様が観察できます。
今日は3、4歳くらいの男の子が“开裆裤”をはいているのを見かけました。珍しいなあ、今でもはいている子がいるんですね。“开裆裤”というのは股の部分が割れていて、お尻が丸見えになっている中国の幼児用ズボンです。どんな見た目か気になる方は、Google画像検索で“开裆裤”と調べてみてください。後ろから見ると子どものかわいいお尻が見えるような構造で、ズボンを脱ぐことなくしゃがめば素早く用を足せる仕組みになっています。その昔、中国ではオムツだと洗う手間や使い捨てで金がかかるため“开裆裤”が一般的でした。
今ではほぼ見かけなくなりました。だって農村部ならまだしも、都市部のそこらで大小便をするわけにはいきません。それに常に肌が露出している“开裆裤”は感染症の原因にもなり得ます。ここ最近は全く見かけない絶滅危惧種になっていたわけですが、まだ残っていたんですね。
調べてみると、今でも“开裆裤”をはかせる親がいる理由のひとつに「オムツの交換がしやすいから」というものがあるそうです。なるほど、オムツをした上で“开裆裤”をはかせるわけですね。確かにオムツの交換ってズボンを脱がせ、肌着を脱がせ……みたいな手順が必要なので、それを省けるなら相当楽になると思います。私にも1歳の娘がいるのでよーく分かります。
けれど今日の男の子はかわいいお尻が見えていたので、オムツ交換がしやすいように……というわけではなさそうです。今やメリットよりデメリットが上回りそうな“开裆裤”をわざわざはかせるのはなぜでしょう。見る感じ、男の子の両親は私より5歳ほど年上に見えました。もしかしたら自分たちが小さい頃によくはいた懐かしい“开裆裤”を子どもにもはかせたかった、そんなところかしら(^^;)。
でも、私も何となく理解できます。この冬、娘に半纏を着させたくて、日本に一時帰国をした際に衣料品チェーンの「しまむら」を回ったのですが、手に入らなかったんですよね。私も妻も小さい頃から半纏を着て育ち、私にいたっては今でも愛用しています。愛着のある半纏を娘にも着せたらかわいいだろうなあ……と何となく思ったんですけど。もう半纏の季節は過ぎてしまったので、娘の半纏探しは次の冬シーズンにお預けということになりそうです。



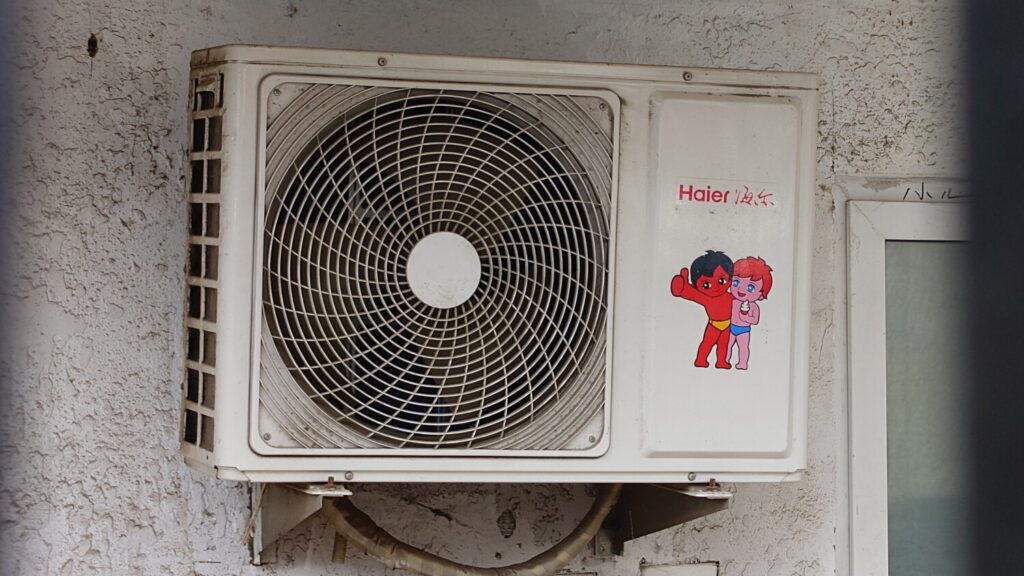
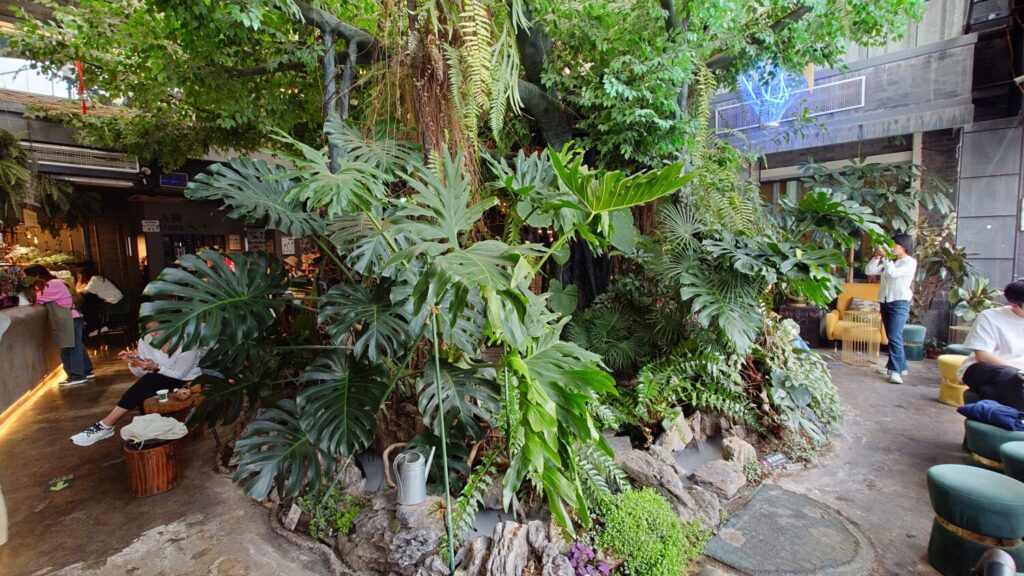


最近のコメント