今日は「北京動物園」に行きました。例によって事前予約が必要なので、午後の入園枠を予約。当日だと予約がいっぱいなんじゃないかと心配しましたが、全く問題ありませんでした。
チケットは別料金のパンダ館とセットで大人1人19元(約380円)。へええ、やっす~い。ちなみに日本はどうだろうと上野動物園を調べたら、こちらも大人1人600円。動物園ってそんなに安いんですね。いずれも公立なので地元自治体や地元政府の補助が入っているのかも。ありがたいことです。

中国はどこに行っても人が多いので「動物より人間のほうが多かったらどうしよう」なんて思ったのですが、心配無用でした。と言うのが、北京動物園は敷地がびっくりするほど広いからです。その面積は90ヘクタール、上野動物園の約6倍です。その歴史も約120年なんだとか。でも上野動物園は1882年開園(約140年前)というから、もっと驚きました。

まずは向かったのは「パンダ館」(“大熊猫馆”)。ここだけは別料金のエリアです。通常のチケットに加えて5元(約100円)かかり、私たちは最初からセットになったチケットを買いました。北京動物園にはジャイアントパンダが10頭いて、うち9頭が観覧できるようになっています。

宙を見つめたままジーッと固まったパンダ、まるでぬいぐるみのようです(^^;)。さすが中国でもパンダは大人気で、たくさんの人が窓枠に張り付くようにパンダに見入っていました。
ちなみにパンダを見るのに最適なのは午前中なんだそうです。特に朝食の時間は一番動きが良くて、ムシャムシャ竹を貪り食う様子が見られるんだとか。一方、午後は昼寝してしまうことが多いそうで、確かに私たちが見に行った午後2時頃はじーっとしていました。この固まったパンダもウトウトしていたのかもしれませんね。

今日、日本では和歌山県白浜町のパンダが中国に返還されます。残るパンダは上野動物園の2頭となり、この2頭も来年2月には返還される予定なので、インターネット上では「日本からパンダがいなくなってしまうのでは」なんて話題になっています。
中国政府は世界的に人気の高いパンダを「仲良くなりたい国」に送ることで友好を示すなど、外交カードに使ってきました。日本に初めてパンダが来たのも1972年に日本と中国が国交を正常化させたとき。このとき日本に来たカンカンとランランは北京動物園で「最も容姿と性格が優れている」として選ばれたんだそうです。もっともカンカンとランランは現在の「ブリーディング・ローン形式」ではなく、返還義務のない譲渡でしたが。
来年以降、本当に日本からパンダがいなくなってしまうのか――それは分かりませんが、いずれにせよ中国政府の采配次第です。私の個人的な予想だと、一時的にパンダがいなくなる時期があってもまた来るんじゃないかな。日本人のパンダ好きは中国でもよく知られています。シャンシャンが中国に返還される際、上野動物園でたくさんのファンが涙ながらに見送ったニュースは中国でも報道されました。中国にとって日本は仲良くしておきたい隣国ですから、友好の使者としてパンダが果たしてくれる役割も大きいはずです。

続いて来たのは猿山。広いガラスで囲われ、中にはサルがたくさんいました。赤ちゃんザルが取っ組み合ったり、器用に山をスルスルと登ったり、とてもかわいかったです(^^)。
見た目はニホンザルのようですが、長めの尻尾があるのでそうではなさそうです(ニホンザルに尻尾はありませんね)。看板には“猕猴”と書いてありました。これはニホンザルを含む「マカク属」全体を指す中国語の名称のよう。おそらくですが、アカゲザルじゃないかと思います。

ホッキョクグマ館(“北极熊馆”)があったので、こりゃあ涼める!と思って入ってみました。すると全然涼しくない(^^;)。いや、人間はいいんです。けどホッキョクグマは大丈夫なのかしら。のぞいてみると、ホッキョクグマも外気にさらされた「ただの庭」のようなスペースに放されていました。うーん、北京の夏はホッキョクグマにはちょっと厳しいんじゃないかあ。実際、ホッキョクグマはスペースの端のほうでへたれてしまっていました。まるで「たれぱんだ」です(ふるい?)。

特徴的な見た目の鳥。中国語では“双垂鹤鸵”と書いてありました。「鶴」(つる)なのか、「駝」(だ)=ダチョウなのか、よく分かりません。調べてみると日本語では「ヒクイドリ」(火食鳥)と言うのだそうです。不思議な名前ですが、一説には喉の赤い肉垂が「火を食べている」ように見えるから名付けられたんだとか。臆病な一方、気性が荒い鳥として知られていて、インドネシアやオーストラリア北部に生息しているということです。
ちなみに、このあたりで娘はベビーカーの上でウトウトしだして眠ってしまいました。いつもお昼寝している頃の時間ですし、たくさん歩いたので疲れちゃったのかな。本当はこのあとキリンなんかも見せてあげたかったんですけど、しばらく大人だけでの動物鑑賞になりました。

キリンのいるエリア、世界中のサルがいるエリアなどを経て、ペンギンのエリアに来ました。この辺りでお昼寝していた娘が起きました(^^)。
ペンギンは中国語で“企鹅”(企鵝)と言います。“鹅”(鵝)はガチョウという意味ですが、一文字目はなぜ“企”だと思いますか。日本人はあまり意識しないと思いますが、“企”という漢字には「かかとを上げてつま先で立つ」という意味があり、それが転じて「つまだって待ち望む」という意味があります。つまり“企鹅”(企鵝)という中国語には「まるで何かを待ち望むかのようにつま先で立つガチョウ」という意味があるのです。このペンギンの姿を見ていると何となく分かる気がしますね。

こののべーっとした生き物、オオサンショウウオです。日本では国の天然記念物に指定されています。私の地元・岡山の北部にはオオサンショウウオが生息している地域があり、方言で「ハンザキ」と呼ばれています。今では生息数を減らしているようで、かく言う私も野生のオオサンショウウオを見たことはありません。
ただ北京動物園に展示されているのは、厳密にはオオサンショウウオではありません。こちらは「チュウゴクオオサンショウウオ」と言って、見た目はそっくりですが違う種類なんです。今、日本各地では持ち込まれたチュウゴクオオサンショウウオの一部が逃げ出し、日本固有種のオオサンショウウオと交雑して「中間の見た目」のオオサンショウウオが増えていて問題になっているんだそうです。

中国に生息する「ヨウスコウワニ」。口吻というんでしょうか、鼻先が短くて可愛らしい顔をしています(^^)。その名前の通り、揚子江に生息しているそうです。ユーラシアに唯一生息しているアリゲーター科とのこと。人間を襲った記録はなく、極めておとなしい性格なんだそうです。日本でもカイマンくんなんて話題になりましたが、ヨウスコウワニならペットして飼えそう?
北京動物園、午後からの入園でしたが、しっかり楽しめました。トータルでどのくらいかな?4時間くらい滞在したかもしれません。北京動物園は「動物の展示スペースがある巨大な公園」みたいな感じでした。ベンチも多いし、木がたくさん植わっているので日陰も多くて助かりました。中国の観光地はどこに行っても“人山人海”ですが、ここまで敷地が広いとゆっくりできますね。また来てもいいなと思いました(^^)。














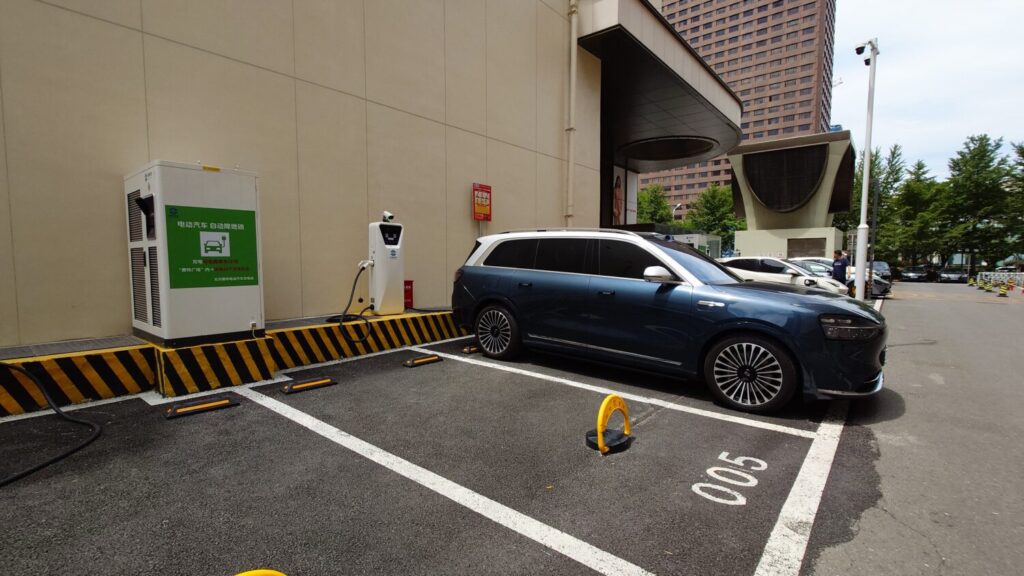

最近のコメント