最近旧ツイッター、もといX(エックス)で話題になっていた本。妻も読んだそうで、私もAmazonのKindleで購入して読んでみました。綿矢りささんの「パッキパキ北京」です。
作品の舞台はコロナ禍真っ只中の北京。ちょうど2022年の年末、北京で新型コロナウイルスが感染爆発した頃から始まります。私も同じ時期に北京で過ごしていましたから、いろいろと我が事として思い出されることも多く、楽しく読みました。
主人公は36歳で子どものいない駐在妻*1。中国入国後の隔離*2を経験し、北京に到着してから贅沢三昧の日々を過ごします。すでに北京で3年働く頭ガチガチサラリーマンの夫よりよっぽど北京暮らしをエンジョイする物語です。主人公の女性は中国語が全く出来ないのに中国のネット通販「タオバオ」(“淘宝”)や中国版インスタグラムとも呼ばれているSNS「小紅書」(“小红书”)を使いこなしていて、読んでいるだけで中国の「今」が分かります。
北京という街の特徴についてもよく分析していて、うまい表現で書かれているのを見ると、いや、言い得て妙だなあと感じます。
北京では地方出身者が肩身の狭い思いをしてるとか、故郷を恋しく思って帰りたくなるとも聞いていたから、北京は田舎から出てきた人間を打ちのめすほどの大都会のコンクリートジャングルかと思ったら、意外と土くさい素朴な雰囲気が街にも人にも残っている。これなら行ったこと無いけど上海とか、または東京の方がよっぽど、田舎から出てきた人間を不安にさせる近未来的な発展具合と騒がしさがあるんじゃないかと思った。
パッキパキ北京/綿矢りさ
そうそう、北京って今や世界第2の経済大国・中国の首都なのに、なんかこう、巨大な田舎みたいなところがあるんですよね。冬になると立派なショッピングモールの入口に防寒用の巨大な布団みたいなものが下がっていて、ちょっとダサい(笑)けど、これが室内の温度を保ったり、あと防風にもなったりして良いんです。東京ではまず見られないと風景かと思います。
あとは新型コロナの感染爆発した時期を経験した人なら「分かる分かる」「大変だったなあ」と思い出される描写もたくさんありました。
夫は少しも北京に馴染んでない。会社と家との往復で、仕事は難なくこなしているけど、それ以外はほとんどほとんど家に閉じこもり気味だった。夫が巨大な都市北京のめぼしい場所にまだ行ってないと知り、少しからかうと、「君が来るほんの少し前までは、コロナ感染対策が厳戒態勢で、とてもじゃないが街をうろつける雰囲気じゃなかったんだ。マンションからほとんど出ないで過ごして、仕事や会議もオンラインでこなして、毎朝氷点下十度以下の極寒のなか、ときには一時間以上も毎日場所が変わる野外のPCR検査所の長蛇の列に並んだんだ。遊ぶ余裕なんかこれっぽっちも無かったよ」とすごい剣幕で反論が返ってきた。よっぽど苦労したらしい。
パッキパキ北京/綿矢りさ
わはは、そうそう。中国の「ゼロコロナ」政策、特に末期の頃は店がどこも閉まってしまい、開いている店も24時間以内のPCR検査の陰性証明を要求されるなど本当に大変でした。
しかし、ほどなくして「ゼロコロナ」政策は急転直下、光芒一閃の政策変更をするんですよね。PCR検査はなし崩し的に求められなくなり、入国後の隔離もなくなりました。中国に来たのが「ゼロコロナ」政策の前か後かで抱く印象は本当に違うと思います。
中国に住んでいて、かつ「ゼロコロナ」政策を経験した身としては面白く読みました。ただ、ストーリーとしてはどうでしょう。最後も何だかあっさり終わってしまって「え、もう終わり?」と思ってしまい、中国(特に北京)に住んでいないとか、あるいは中国について前提知識が少ない方は楽しめるのかなあと感じました。あるいは、この作品は綿矢りささん自身が北京滞在時に見聞きした経験が詰め込まれているということですから、もしかすると純粋に「エッセイ」を読んでいるつもりで楽しめば良いのかも知れません。
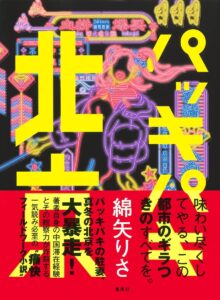


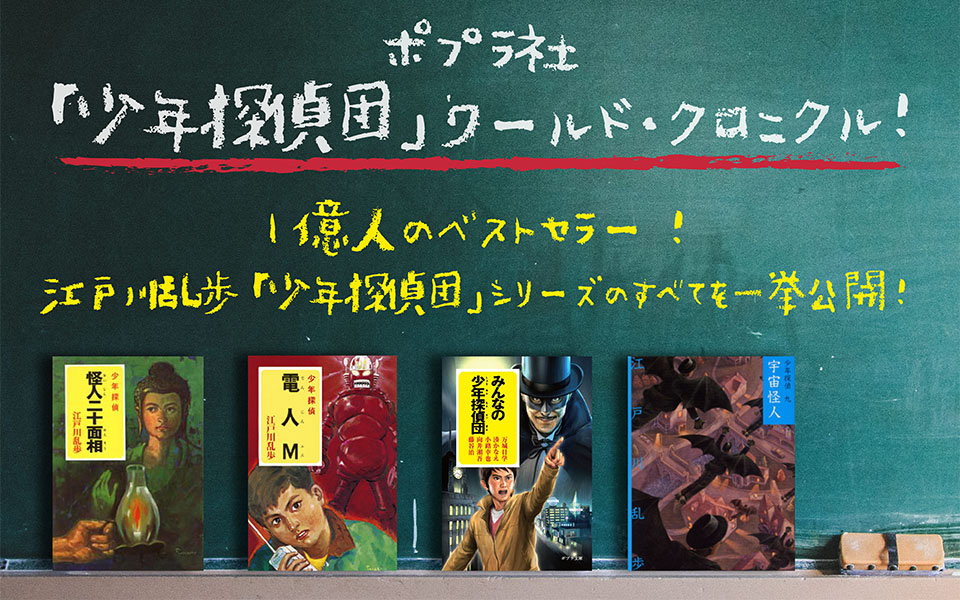
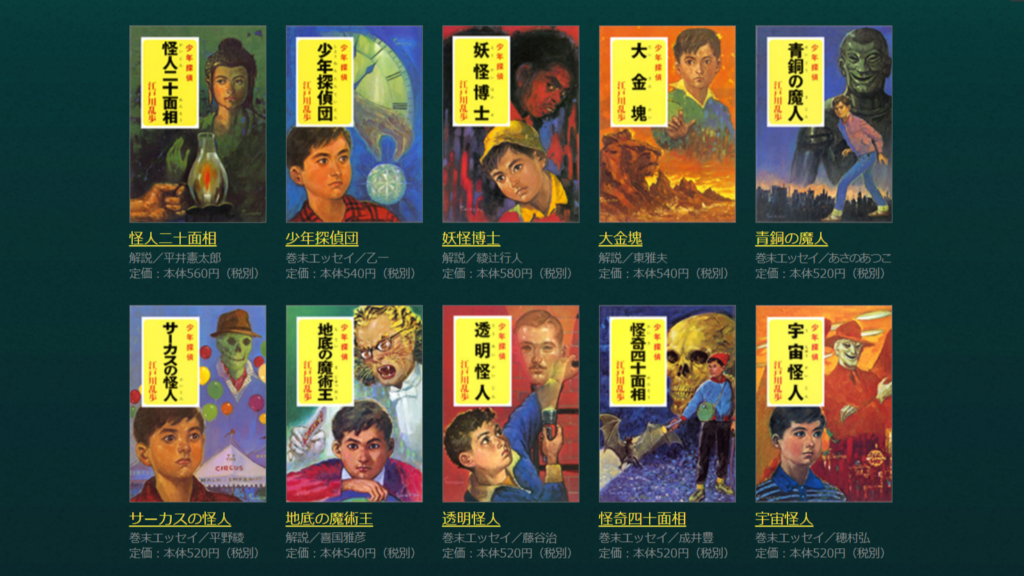
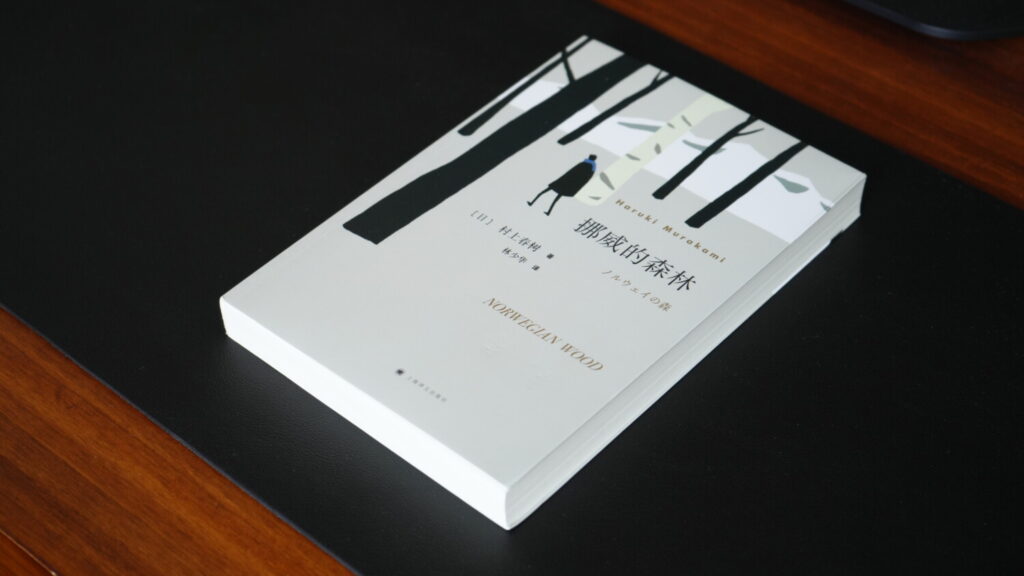
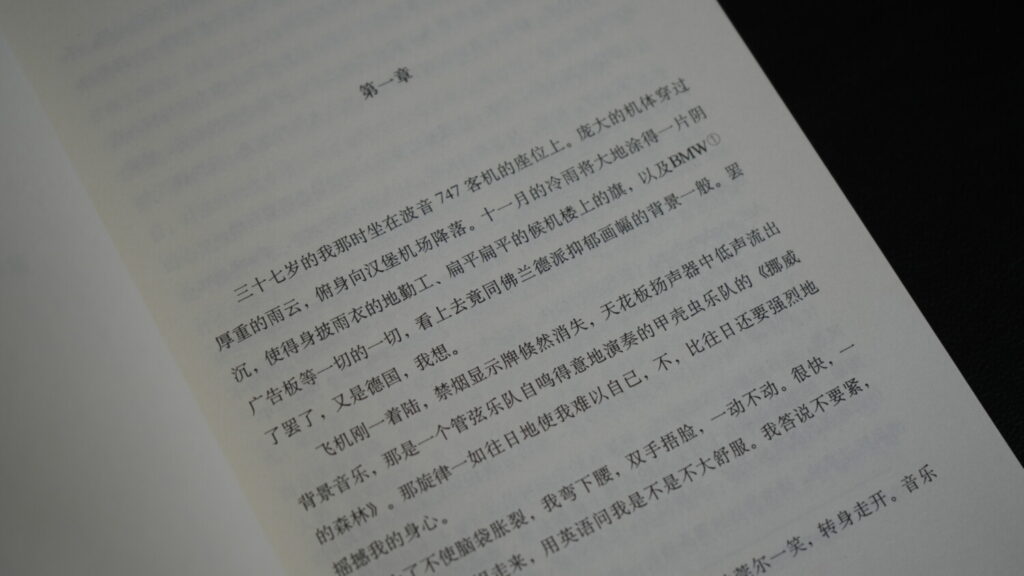
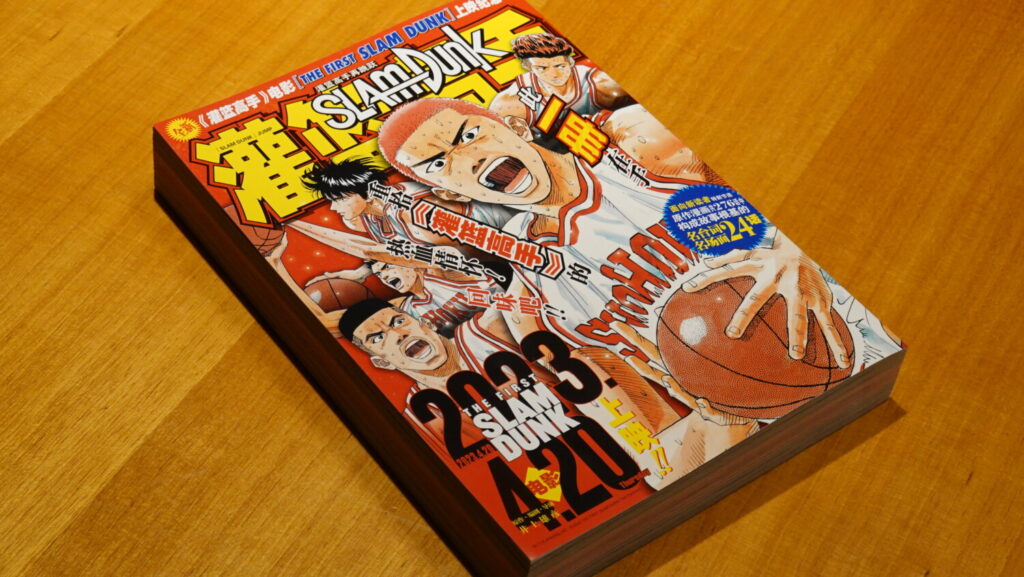
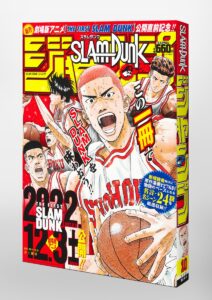

最近のコメント