最近雨が続いています。先週の金曜日に降って、今日も雨。
北京は雨が少ない地域です。最後に傘を差したのがいつだったか思い出せないくらい。調べると、北京の年間降水量は約600mmで、東京の約1500mmや大阪の約1700mmに比べると半分以下です。大陸性高気圧、北京の場合は「シベリア高気圧」に覆われているので雨が少ないそうです。
昨日は二十四節気の1つ「穀雨」でした。穀物の成長を助ける雨という意味です。この頃には田畑の用意が整い、これに合わせて雨が降るんだそうです。こうして本当に雨が降るんだから、昔の人は賢いなあとつくづく感じさせられます。
ちなみに中国で穀雨は“谷雨”と書きます。え、穀物の雨なのに、なんで谷になっちゃうの?と思われるかもしれません。今の中国では「簡体字」といって簡略化した漢字が使われています。「穀」という漢字は複雑で難しいので、同じ発音の「谷」に統一されてしまったのです。だから中国では穀物のことを“谷物”と書きます。こうした漢字は他にもあって、例えば麺は“面”、後は“后”、髪は“发”(発)に統一されました。
けど、味気ないですよね。穀雨という漢字だからこそ「春の雨が穀物を潤す」という場面が思い浮かぶのに“谷雨”ではイメージが全然違ってしまうと思います。漢字を簡略化してしまった弊害です。台湾や香港では未だに伝統的な漢字*1が使われているので、日本と同様に“穀雨”と書きます。
ちなみに学生時代に台湾へ旅行に行った際、面白いエピソードを聞きました。とある麺屋が“帥哥下麵很好吃”(イケメンの茹でた麺は超うまい)という店名を付けたそうです。ただし、これが中国だと“麵”が“面”になるなので“帅哥下面很好吃”という表記になります。“下麵”(麺を茹でる)が“下面”になると、これには「下半身」という意味もあり――“帅哥下面很好吃”で「イケメンの下半身は超うまい」という意味になっちゃうのです。これだと麺屋が別業態の店と誤解されちゃう?……いやいや、そんなことはないでしょうけど、これも漢字を簡略化してしまった弊害かと思います。
| *1 | 簡略化された漢字「簡体字」に体し、伝統的な漢字は「繁体字」と呼ばれます。 |
|---|
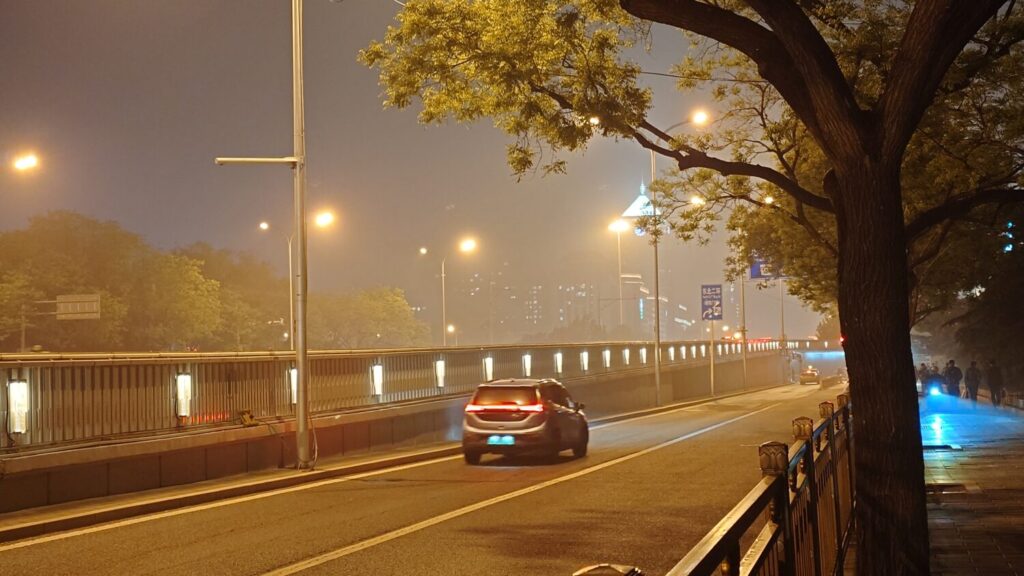




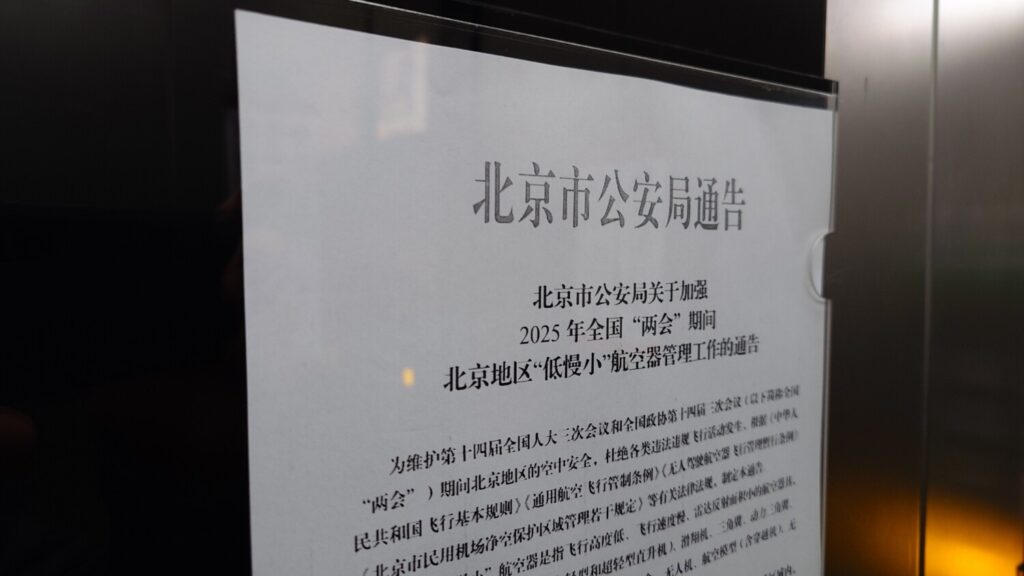



最近のコメント