私が北京に留学していたのはたかだか11年前だが、それでも当時と比べるとたくさんの変化を感じる。どれも私の主観だから、他人からすれば「どうでもいい変化」かもしれないけれど(^^;)。
そのうちのひとつ、多くの人がコーヒーを飲むようになったと感じる。
11年前の北京はコーヒーを好んで飲む人がまだ少なかった。日本の純喫茶のようにコーヒーだけを出す店は無かったし、喫茶店というと文字通り「茶」を楽しむ場所だった。スターバックスやコスタコーヒーといった海外のカフェチェーンは当時からあったが、中国人たちは専らカフェモカやココアといった甘い飲み物が目当てで、コーヒーを飲む人は少なかったように思う。
そうしたなか例外的に珈琲の名を冠する店があった。その名も「上島珈琲」(”上岛咖啡“)、北京だけでなく中国各地で見かけたことを覚えている。

北京の上島珈琲(2011年1月撮影)
日本で上島珈琲と言えば、神戸に本社を置くUCCが経営する「上島珈琲店」だ。

上島珈琲店
美味しいカフェをお探しなら、上島珈琲店へご来店ください。美味しさにこだわりぬいたネルドリップコーヒーで、厳選された季節のデザートやお食事メニューをゆっくりお楽しみいただけます。近くのカフェをお探しなら、ぜひ上島珈琲店へ!
一方、中国の上島珈琲は全くの別物。どうやら台湾発祥のようで、中国国内で約1000店舗と派手に展開し、現地で知らない人はいないほどメジャーになっている。日本の上島珈琲店も中国に進出はしているものの、皮肉にもこちらのほうが圧倒的な認知を得ている。

北京の上島珈琲(2011年1月撮影)
ニセモノかどうかはさておき「珈琲」という文字が店名に入っているのだ。それなりのコーヒーを出してくれるんじゃないかと期待して、留学時代に一度入店してみた。
私の入った店舗は暗く怪しい雰囲気が漂っていて(笑)それぞれのボックス席がすだれで仕切られ目隠しのようになっていた。メニューを見ると喫茶店というよりは、ファミレスのようなラインナップ。メニューのどこにコーヒーが書いてあるのか探してしまうほどだった。
肝心なコーヒーだが、まるでお湯のように薄い味で全くおいしくなかった。おそらくブラックで飲む人が少なく、どうせ砂糖とミルクを入れるので、コーヒーそのものはあまり重要ではなかったのだろう。当時は中国でこういう薄いコーヒーによく出くわした。これならインスタントコーヒーのほうがまだましだ、と泣く泣く帰ったのを覚えている。

なぜそんなことを思い出したかというと、今日、会社近所にあるセブンイレブンでコーヒーを買ったからだ。写真はMサイズ(”中杯“)で、10元(約200円)。たっぷり入っていて、味もまあまあ。少なくとも上島珈琲(『上島珈琲店』ではなく)と比べれば雲泥の差だ。
そもそもセブンイレブンだって私の留学時代にはほとんどなかった。それが今や北京の至る所にできて、そこでコーヒーが買える。ちょっと大げさかもしれないけど、留学当時にコーヒー難民だった私からすれば隔世の感を禁じ得ない。それだけ今、中国でコーヒーが飲まれるようになっているのだ。

中国国産のカフェチェーンも多数生まれている。
その代表例が「ラッキンコーヒー」(”瑞幸咖啡“)。わずか4年前に北京に1号店を出したばかりだというのに、すでに7000店舗近くを展開し、数だけならスターバックスを凌いでいる。実際、北京の街を歩いていてもあちらこちらで見かける。行ってみると、店舗の内装はおしゃれだしコーヒーの味もまずまず。何も知らずに店を訪れた人はまさかラッキンコーヒーが中国国産のカフェチェーンとは思わないんじゃないかなあ。
今や、中国のコーヒー市場は「戦国時代」だ。中国人たちのコーヒーを飲む舌はどんどん肥えてきていて、この国で生き残っていくのは簡単ではないだろう。鎬を削る企業の皆さんは大変だろうけど、コーヒー好きとしてはありがたい限り。これからの中国駐在生活、いろんなコーヒーを飲み比べるのが楽しみだ。






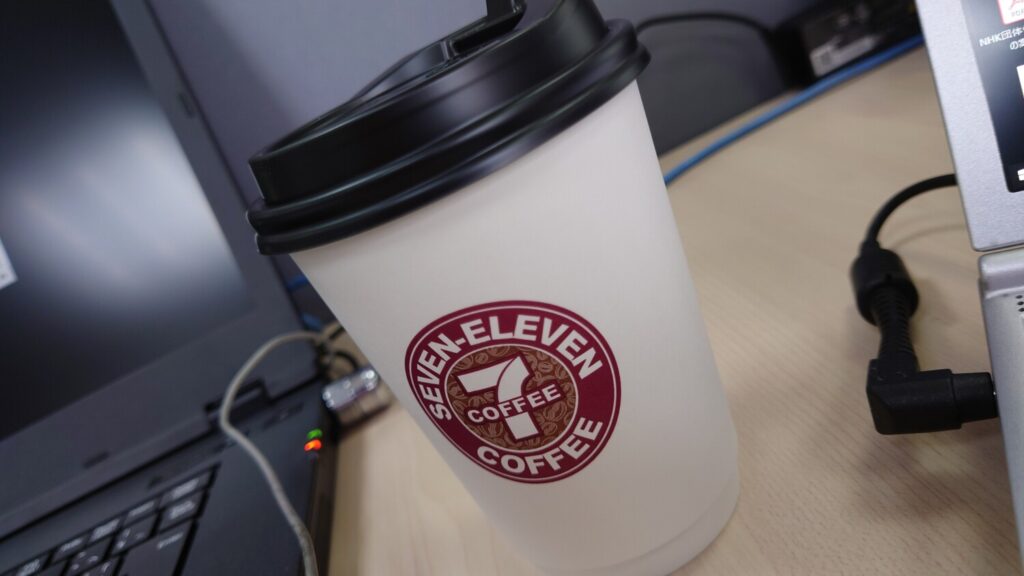

最近のコメント