仕事でおつきあいのある、四国財務局の方に地方創生に関するシンポジウムのお誘いをいただき、参加してきました。
対象としているのが若手の公務員ということで(ちなみに私は公務員ではありません)四国各県から参加者がいらっしゃいました。あまり詳しくないのですが、40代くらいまでは若手に入るそうで、私なんかよりもよっぽど年上のベテランっぽい方もいらっしゃいました。
私が興味深くお聞きしたのは、ことでん=高松琴平電気鉄道の真鍋康正社長のお話。公共の名の付く「公共交通」ですが、運営しているのは民間。どう考えても純粋な民間ではもたない、やっていけないのに、そこに行政との理解にギャップがあると指摘します。
その一例となっているのが両備バスが赤字31路線の廃止届を国に提出した問題。両備バスにとって主要幹線である西大寺線に低価格均一運賃の競合他社が全く同等の路線営業を申請し、それが認可される見通しとなったのです。そのため、主要路線が打撃を被る両備バスが健全な経営を続けるために輸送密度が低い路線を廃止せざるをえないとして、およそ40%もの路線廃止を届け出しました。
両備バスは民間ではあるけれども、公共交通の使命である「人々の足」として輸送密度が低い路線でも運行してきました。それなのに簡単に参入を許してしまえば、末端部のサービスを維持できなくなるのは明らかなはず。「完全自由化なら撤退も自由よ、それでいいの?」という一石を投じた問題だと思います。
真鍋社長はそうした観点からも、ことでんを「理想的な劇的復活」よりも「地道に地域のインフラを担う存在」として維持させるかが重要だと指摘していました。特に少子高齢化が進み、高齢ドライバーによる事故が多発している地方こそ公共交通が担う役割は大きいはずなのに、日本人の中にはどうしても「公共交通は都会のもの、地方はクルマ社会」という誤解があるとのこと。うーん、80になる祖母が今でも毎日のように車を運転する私としても考えさせられます。公共交通を巡る問題は会社と行政だけでなく、私たち一般市民も考えを改めていく必要があるように感じました。
シンポジウムに参加されている皆さん、本当に勉強熱心な方ばかり。6人の方が講演してくださったのですが、私は最後あたりで集中力が切れてしまっていました(笑)。とはいえ、貴重な機会をくれた四国財務局の方には感謝です。運営も本当にお疲れさまでした。
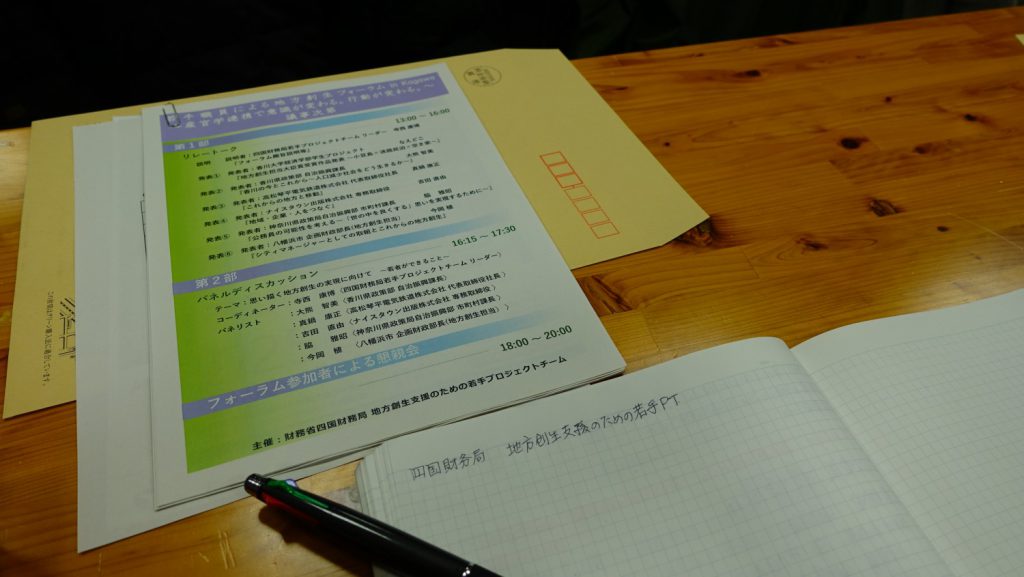







最近のコメント